
部長、おはようございます!
…どうされました?何かお困りのようですが
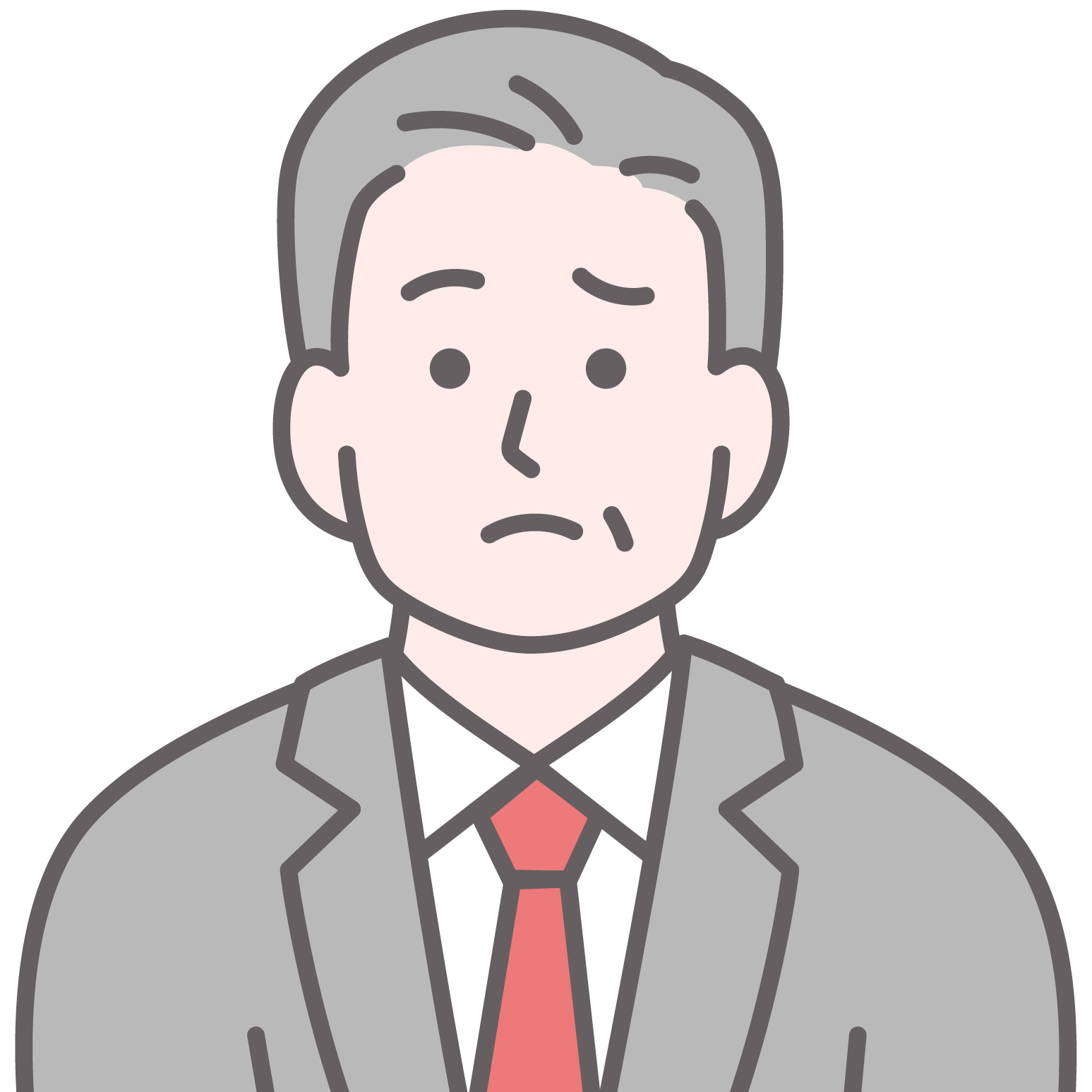
おはよう…
そうなんだよ
新人のA君が何の連絡もなくもう3日も出社しないんだ
何回電話しても出ないし、折返しもないんだよね

確かにお休みの届出は出されていませんね!?
何かあったのかな…?
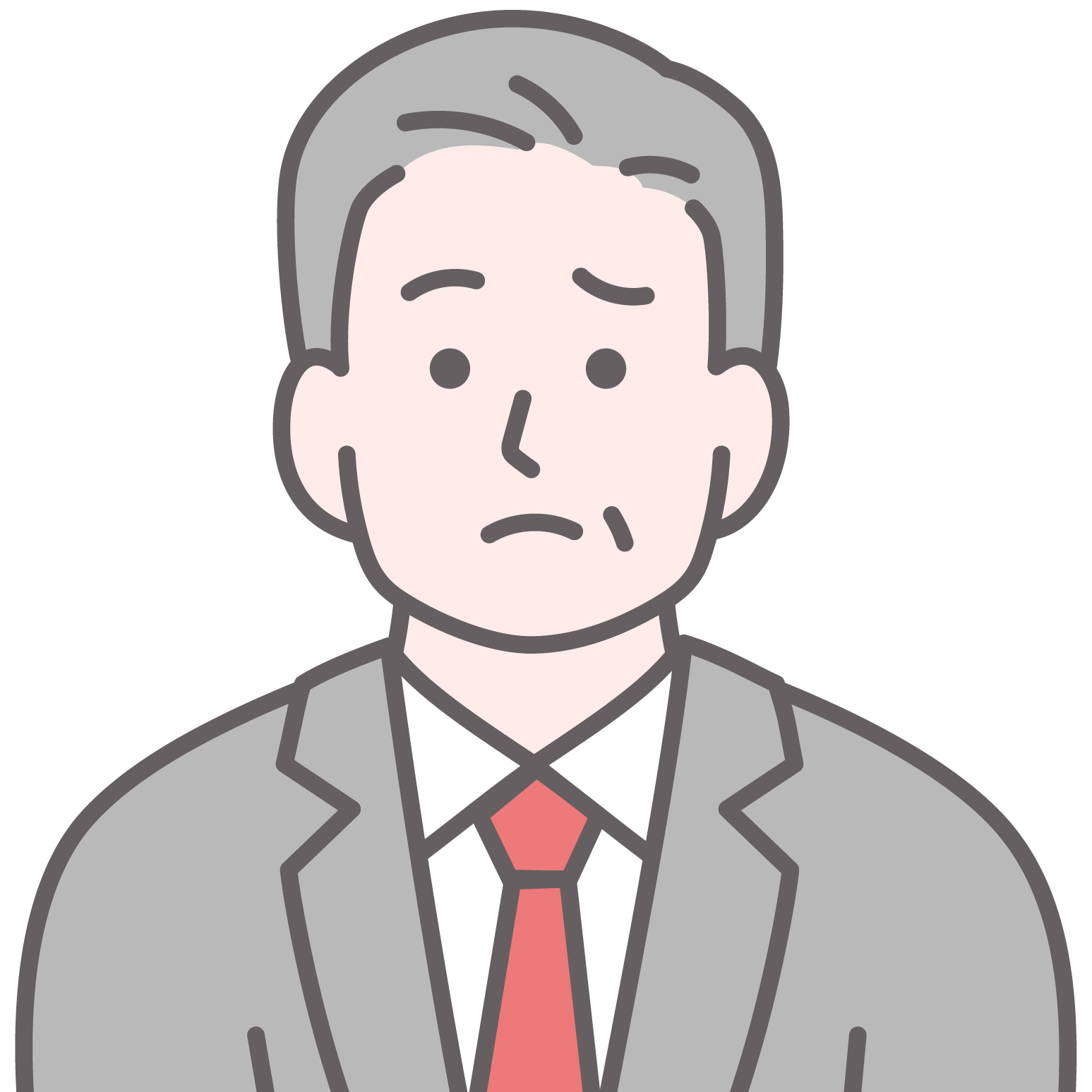
もしこのまま音信不通の状態が続いたら
解雇しちゃって大丈夫だよね?
連絡返してこないってことは、辞める気なんだろうし…

確かに、このまま会社に来ない可能性はありますが…
解雇しちゃって大丈夫なのかな…?
顧問社労士に聞いてみますね
社員が突然出社しなくなることは、残念ながら今どきあまり珍しいことではありません。
私の経験では比較的若い方に多く、これまで何社もこういったご相談を受けています。
冒頭の会話のように、
「出社しないし連絡もつかない」→「辞める気だからだろう」→連絡がつかないけど退職の手続実行!
という流れで軽く考えがちですが、これ実は実務上、かなり厄介な問題なんです。
ありがちな行方不明への対応パターン
最初は突然の無断欠勤から発生します。
社長や上司が電話やメール、チャット等で連絡を取ろうと試みるものの応答はなく、折り返しの連絡もありません(LINEだと大体既読にならない)。
心配して家を訪ねても、誰も出てきません。
電気のメーターを見るとブンブン勢いよく回っているので、中に誰かいるかも知れませんが…。
その後何度か電話やメールをし、時間帯を変えて家を訪問してみるものの、事態は変わらず。
「これだけ連絡したし家にも行ったけどダメだ。もう出社するつもりはないだろう」
諦めて退職のフェーズに移ります。
ここでふと「退職っても、どうやって退職扱いにするの?」と疑問に思うか、そのまま退職手続を実行してしまうか…。
仮に後者を選択してしまうと、後々労務リスクが発生する可能性があります。
根拠なく退職扱いにするリスク
来なくなったからといってすぐに退職の手続きをしてしまうと、労務トラブルに発展する可能性があります。
(なかなかないケースかも知れませんが)行方不明だった社員が1か月程経って何事もなかったかのように社員が出社してきたとしたら…。
もう退職の手続をしてしまったし、「今更何しに来たの?」という感じになるでしょう。ところが。
「確かに連絡ができなかったが急病で倒れて仕方がなかった!辞めたつもりはない!不当解雇だ!」
そう言われたときに、あなたは法的に問題ないという主張ができるでしょうか?
もしかしたら、本当に何か正当な事情があって連絡が取れなかったのかも知れません。
「多分辞める気だろう」はただの憶測であって、憶測による手続にはそもそも何の根拠もありませんよね…。
行方不明になった=もう出社しないだろう、で退職処理するのは危険!
就業規則に従って解雇すればいい?!

就業規則には解雇(懲戒解雇を含む)の規定がありますよね。
そこには、「無断欠勤○日以上で解雇する」という趣旨の条項が定めてあったりします。
「多分辞めるだろう」が根拠にならなくても、無断欠勤している事実はあるじゃないか。
就業規則の定めを適用して、解雇(又は懲戒解雇)すれば済むんじゃない!?
という疑問、浮かびません?
実は無断欠勤を一定期間続けた場合に解雇になるという規定を適用して、本人の行方不明であるのに解雇してしまうことは、極めてリスクが高いのです…。
そもそも「解雇」とは?!
「解雇」って、そもそも何ですか?
これをまず整理しておくと、どんなリスクがあるのかが見えてきます。
まず、雇用期間に定めがない場合の解雇(例えば正社員)については、民法第627条にその根拠があります。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
民法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089 より抜粋
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
これはよく、社員が退職する際に根拠として出てくる規定ですね。
例えば、会社に退職届を出したけど人手不足を理由に辞めさせてもらえない…というようなケースで、退職できる根拠として挙げられます。
話がちょっと飛びましたが、主語が「当事者」になってます。
雇用契約の当事者は(分かりやすく表現すれば)会社と社員なので、社員側だけではなく、会社側からも雇用契約の解約を申し入れることができる…ということです。
そして、「解約の申入れをすることができ」、雇用は「解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する」となっています(ちなみに完全月給制の場合は民法第627条第2項が適用されるので解約の申入れの時期が違ってきますが、欠勤しても給料を控除しない一般的に完全月給制を採っていることは稀かと思います)。
つまり、会社から雇用契約を解約する申入れをしたら、その日から2週間経てば契約終了になる(会社からの一方的な申入れで契約終了)ってことです(これが解雇)。
※嘘だぁ!解雇ってすごく難しいはずじゃないか!という疑問については改めて別記事にでも…
解雇の通知は、社員に届かないといけない
解雇の意思表示は会社から一方的にできることが分かりましたね。
じゃあ何が問題なんだ!?リスクが発生する余地がないじゃん?
と思われるかも知れません。
ところが、解雇の申入れは相手に届かなければ効力がありません(民法第97条第1項)。
(意思表示の効力発生時期等)
民法 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089 より抜粋
第九十七条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
社員がまったくの行方不明なら、解雇の意思表示が届かないため、解雇ができないということになってしまいます(この場合でも、公示送達という手段で意思表示が届いたことにできるんですが…手間がかかります)。
とりあえず郵便が自宅に届いたからOK
身元保証人に解雇予告通知を送ったからOK
ということできれいに片付く問題でもないため、慎重な判断が求められます。
え?連絡が取れないのに…厄介だなー!
これを読んだらそう思われません?!
解雇は相手に届かないと成立しないので、まったく居場所が分からなくなった社員を解雇するのは難しい!
社員が行方不明になった時の対応
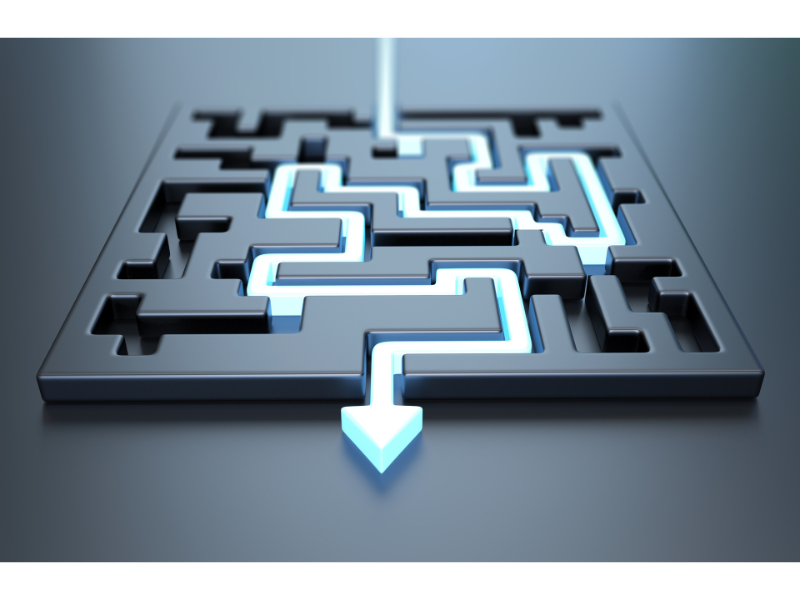
では結局のところ、どの様な対応をすればいいんでしょうか?
まず重要なのは、やはり予防です。
就業規則の退職事由に行方不明を加える
まず備えとして、就業規則の退職事由に行方不明になった時の定めをしておきましょう。
解雇の事由ではなく、退職の事由なのがポイント。
解雇ではなく自然退職とする意味は、後々不当解雇であるという主張を予防するためです(解雇の意思表示は相手に到達しないといけませんでしたね)。
例えば「行方不明となって連絡が取れない場合は1か月で退職となる」というような規定を定めます。
就業規則であらかじめ労務トラブルを予防することがいかに重要かが分かりますよね!?
就業規則の「退職事由」として、行方不明を定義しておく!
緊急連絡先を把握しておく
入社の際に、緊急連絡先を入手しておきましょう。
無断欠勤で連絡が取れない場合に、緊急連絡先に安否の確認をしてみるということも考えられます。
複数の方法で連絡を取ることを試みる
さて、ここからは実際に社員が行方不明になった時の対応です。
まずは、複数の方法で連絡を取ることを試みます。
- 電話(留守電になったらメッセージも入れておきましょう)
- メール
- SNS
- 自宅訪問
- 郵便
一度で諦めず、何度も連絡を取ってみます。
いつ、誰が、どうやって連絡を試みたかは、記録を残しておきましょう。
電話やSNSの場合、社長や上司からの連絡には返信がなくても、親しい同僚等の連絡には返信がある可能性があるので、複数人で対応することも考えます。
このように、本当に行方不明で連絡が不可能だったか、という点はクリアするようにします。
できるだけ複数の方法で、繰り返し連絡を取ろうとする!
連絡したことは記録に残しておく!
出社を促す
複数の連絡方法で、出社を促します。
出社を促すメッセージは口頭のみで形が残らない電話は避け、メールやSNS、郵便で形を残します。
郵便は、内容証明郵便で住所宛に郵便を出します。
内容証明郵便は受け取られればその旨が分かりますし、受け取られなければ戻ってきます。
もし受け取りを拒否される場合は、普通郵便でも同様の内容を送ります。
内容証明郵便が受け取られたのにその後も出社せず、連絡が取れない場合は、退職の意思があるものとして取扱う日付を指定して、再度内容証明郵便を出します。
例えば、○月○日までに出勤しない場合は退職の意志があるものとみなす旨の内容にします。
それでも連絡がなく出社もしない場合は、通知に従って退職の手続きを実行します。
内容証明郵便が拒否ではなく、不在等で受け取られずに戻ってきた場合には、(一般的ではないですが)公示送達によるか、やむを得ずリスクを飲み込んでの対応を検討することになります。
内容証明郵便を含む複数の方法で、出社を促す!
退職の意志が確認できる場合の対応
もし連絡がついて、社員に退職の意志がある場合は、必ず退職届を出させるようにします。
文書はパソコンで出力したもので構いません。
退職届が届いたらすぐに、署名(自署で名前を書いていること)又は押印がされていることを確認しましょう。
もし連絡が取れ、退職の意志があることが分かったら必ず退職届を提出させる!
社員が行方不明になった際のリスク管理

社員が行方不明になって音信不通になった場合、気をつけるべき対応を挙げておきます。
残っている私物を処分してもいいか?
行方不明になった社員が会社に残した私物があるならば、相手に返さなければいけません。
勝手に処分しないようにしましょう。
連絡がつかない場合に備えて、やはり緊急連絡先は把握しておくべきかと思います。
残された私物でも、勝手に処分してはいけない!
ハラスメント・メンタルヘルス不調の可能性を検討する
仕事上のストレスを受けて翌日からそのまま出社しなくなるケースがよくあります。
これが普通の業務上の指導によるものならまだしも、ハラスメント(パワハラやセクハラ)やメンタルヘルス不調が原因で連絡が取れなくなった場合は会社の労務リスク管理上、問題があります。
メンタルヘルス不調による欠勤が無断欠勤であるとして諭旨解雇した事例において、裁判で解雇無効となったケースもあります(日本ヒューレット・パッカード事件)。
社員が行方不明になった場合は、その原因を可能な限りで調査し、ハラスメントやメンタルヘルス不調の可能性があるケースにはより慎重に対応する必要があります。
行方不明の原因について、ハラスメントやメンタルヘルス不調が疑われる場合の対応は要注意!
セキュリティ上の問題が起きないように管理する
社員が突然行方不明になった場合、会社が貸与した制服や携帯電話、鍵や通門カード等が返却されないことがあります。
これらについては根気よく返却するように求めていくしかありません。
私が体験したケースでは、本人から折り返しの連絡はなかったものの、経営者が朝出社すると制服がクリーニングされて置いてあったことがありました。
会社のセキュリティ上、万一戻ってこなかったら問題になるツールについては、普段から持ち帰りを禁止する、戻って来なくても悪用を防げる仕組みを構築する等、リスクを考えて管理の方法を検討する方がいいでしょう。
セキュリティ上問題になるツールの管理は、万一に備えた対応を検討しておく!
避けようがない行方不明のリスクは予防が第一
今回は、社員が突然行方不明になるというケースについて説明しました。
このリスクは、会社側の努力ではリスクを完全に取り除くことができません。
リスクが現実に発生した時、予防策をどれだけ実施できていたかがダメージを左右する類のものです。
万一の時にダメージを最小限に抑える予防策を、顧問社労士に相談することがオススメです。
また、社会保険労務士事務所スリーエスプラスでは、労務リスクを低減させる就業規則の作成の他、実際に顕在化してしまった労務リスクの相談対応も行っています。
労務トラブルで困る前に、そして困った時に、ぜひご相談下さい。
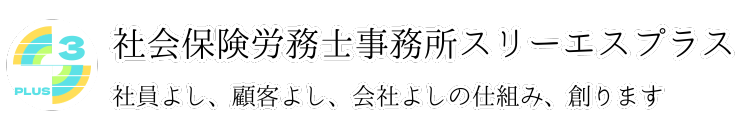

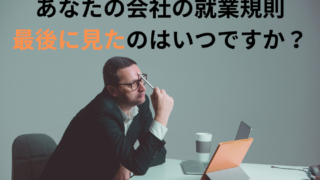


コメント