タイムカードや勤怠管理システムで記録した勤怠記録と、実際の出退勤時刻がズレている。
よくご相談が寄せられるんですが、これ実は、「労働時間」という概念を捉えておかないといけない、結構難しいテーマだったりします。
ですが、難しいからと言って放置しておくと、労務管理上の大問題に発展するリスクも…。
今回は、勤怠記録と出退勤時刻に乖離がある場合の対策と、避けるべきリスクについてポイントを解説していきます。
この記事を読んでポイントを押さえれば、あなたの会社の労務リスクを大きく減らすチャンスになります!
そもそも労働時間とは?
え?働いてる時間のことじゃないの?!
と思われるかも知れません。確かに、そうです。
では、以下の時間は労働時間でしょうか?それとも、労働時間ではない?
- 作業服に着替える時間
- 研修を受けている時間
- 仕事に関する勉強をしている時間
そんなの、労働時間になる訳ないじゃん!
もしそう思われたなら、残念ですがあなたの会社の労務リスクは大きいです。
上の例は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に記載された一例です。
労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たる。
そのため、次のアからウのような時間は、労働時間として扱わなければならないこと。ア 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」抜粋
イ 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
ウ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000149439.pdf
囲みの中、太字にした部分に注目を。
すごくざっくりと表現すると、会社から明確に指示されたり、特に指示はないものの義務であったりするタスクを処理する時間は労働時間であると言っています。
このことについて、同ガイドラインでは次の記載があります。
これら以外の時間についても、使用者の指揮命令下に置かれていると評価される時間については労働時間として取り扱うこと。
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」抜粋
なお、労働時間に該当するか否かは、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんによらず、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであること。
また、客観的に見て使用者の指揮命令下に置かれていると評価されるかどうかは、労働者の行為が使用者から義務づけられ、又はこれを余儀なくされていた等の状況の有無等から、個別具体的に判断されるものであること。
何だか難しいですね…。
これもすごくざっくりと言えば、
- 着替えの時間=労働時間
- 研修の時間=労働時間
- 仕事に関する勉強の時間=労働時間
という「限定列挙されたイコール関係」みたいな単純なものではなく(例えば何の義務もなく、仕事上の不利益を受けることもないが、自分の判断で仕事に関する勉強をする時間は労働時間ではない)、
会社から明確に指示されたり、特に指示はないものの義務でやるタスクは基本的に労働時間ですよ。
労働時間になるかどうかは客観的に見るし、その判断は個別具体的に行いますよ。
という非常にモヤモヤした概念ってことですね。
この、イコール関係で単純処理できないところに、労務リスクが顕在化する余地があるってことです。
指示した場合はもちろん、明確に指示していなくても労働時間になり得る
勤怠記録と出退勤時刻に乖離があるとどうなる?
勤怠記録と出退勤時刻に乖離があると、どういうリスクがあるのでしょうか?
答えは、未払賃金です(他にも36協定違反の可能性というリスクもありますが、今回はそこには触れません)。
勤怠記録が残っている時間分については、給与が支払われているはずですね。
でも、当然勤怠記録がない時間については、給与は支払ってない訳です。問題になるのは、
- 実際の出勤時刻〜出勤の打刻(記録)
- 退勤の打刻(記録)〜実際の退勤時刻
これらの間です。
なぜ、問題になるのか?先程の「労働時間」を思い出して下さい。
要は、勤怠記録が残っていない時間について「本当は労働時間ですよね」と認定され、給与を支払っていなかった労働時間分について追加支払を求められるリスクがあるんです。
言い換えれば「勤怠記録を残さずに仕事してますよね!?」ってことですね。
例えば、退勤の打刻をした後で、仕事上受講義務がある研修を受けて帰宅した場合、退勤の打刻から実際の退勤時間には乖離が生じ、しかもその間は労働時間であり、本当は給与を支払わなければいけないのに、払ってないという事態になる訳です。
ちなみにこのリスクは主に
- 社員からの訴え
- 労働基準監督署の調査
等をきっかけに顕在化します。
勤怠記録と出退勤時刻の乖離は、主に未払賃金発生リスクにつながっている!
勤怠記録と労働時間を一致させる
勤怠記録と出退勤時刻の乖離から生じるリスクを低減させるには
- 労働時間の概念を正しく理解すること
- 勤怠記録と労働時間を一致させる日頃の運用を徹底すること
が有効です。
労働時間の概念を正しく理解すること
これはなかなか簡単ではないのですが、「労働時間とは何か?」ということをきちんと理解することが基本になります。
実際は判断に迷うところでもありますが、明確に指示したタスクはもちろんのこと、「このタスクは仕事上の義務としてやらねばならないことか?」「このタスクをやらないことによって社員が懲戒処分の対象になったり評価等で不利益を被るか?」と考えた時に答えが「YES」ならば労働時間として捉えていいだろうと思われます。
なお、労働時間に該当するかどうかを裁判で争った事例は複数ある(代表的なものに三菱重工業長崎造船所事件等)ので、そこから学ぶこともできますし、厚生労働省等出処が確かなWEBサイトの情報を確認することも有意義です。
勤怠記録と労働時間を一致させる日頃の運用を徹底すること
社員には、「労働時間のできる限り直前に勤怠打刻を行い、労働時間が終わったできる限り直後に勤怠打刻を行う」ことを習慣にしてもらいます。
勤怠記録についてよくあるご質問として、「始業時刻のかなり前に出社して、始業時刻まで新聞を読んだりコーヒーを飲んでゆっくりしているのに、その時間も労働時間になるんですか?」とか「仕事が終わった後に同僚と雑談を続けた後に退勤の打刻をした分まで給与を払わないといけないんですか?」というものがあります。
これらの時間は労働時間ではないので、給与を支払う必要はありません。
ですが、労働時間ではない時間について勤怠記録が残っているので、調査等で疑われる基になります。
逆に、例えば自己研鑽として給与を支払っていなかった時間について、本来労働時間として取扱うべきと判断するなら、そのタスクが終わった後に勤怠打刻をしてもらうよう改める必要があります。
これを徹底できれば、勤怠記録と出退勤時刻の乖離があっても、未払賃金発生のリスクは顕在化せずに済みます(ただ調査の際には乖離が一律に疑われるため、仕事を始める少し前に出社し、仕事が終わったらすぐに退社するのが理想)。
また、これまでダラダラと仕事をしていたのが、メリハリある働き方を意識する方向に変わるというメリットもあります。
なお、勤怠記録は定期的に内容をチェックして、労働時間の認識等に誤りがあれば正しく補正することも大事です。
日頃の管理・指導が労務トラブル予防になる
以上のように、勤怠記録と出退勤時刻の乖離が引き起こす労務リスク対策は、日頃の管理・指導がカギを握っています。
これまで緩い管理しかしていなければ、社員から不満の声が出る可能性もあります。
ですが、労働時間を正しく判別し、正しく勤怠記録を付けなければ、思わぬリスクが顕在化するきっかけになってしまいます。
リスク管理の観点からは、メリハリのついた働き方を求めるマネジメントが大切ということですね。
勤怠にまつわる労務リスク対策は、顧問社労士に相談されるのがオススメです。
また、社会保険労務士事務所スリーエスプラスでは、勤怠管理システム導入支援や、日頃のマネジメント方法についてのご相談に対応しています。
「ちょっと相談してみたいな」と思われたら、お問い合わせフォームからお気軽にお声掛け下さい。
監修:大冨伸之助(社会保険労務士)
広島県社会保険労務士会所属。2004年(平成16年)社労士試験合格、翌年登録。
「社員よし、顧客よし、会社よしの仕組み創り」をテーマに、採用支援・労務相談対応・人事制度設計・バックオフィスのIT化支援を行う。
約10年の社労士実務経験以外に約8年の会計実務経験があり、経営的視点から中小企業の経営者の決断を支える。
”smile” ”speed” “security”を仕事の基本スタンスとし、頭文字を取り事務所名を「社会保険労務士事務所スリーエスプラス」とした。
広島市生まれの呉市育ち。
広島県外に住んだことがなく強めの広島弁が特徴だが、オンラインで全国対応可。
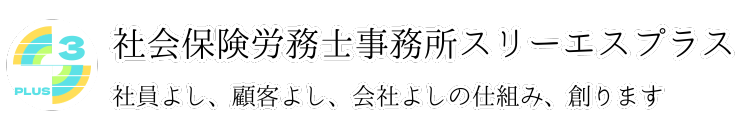



コメント